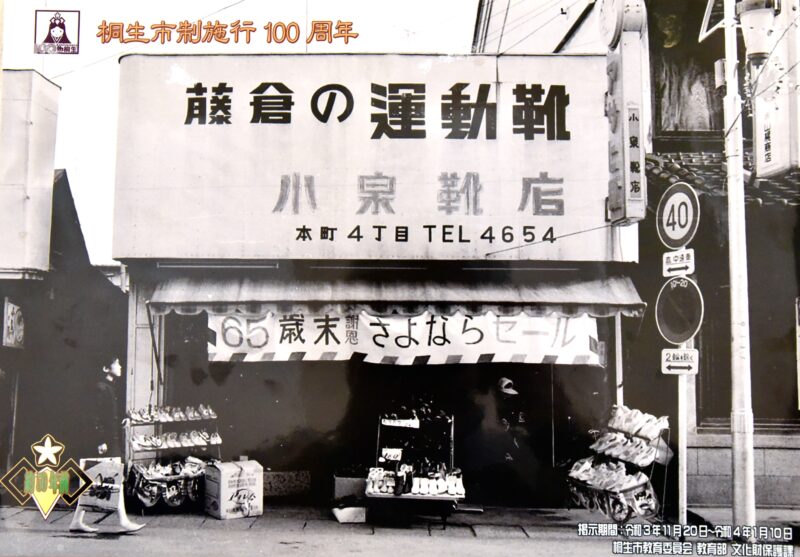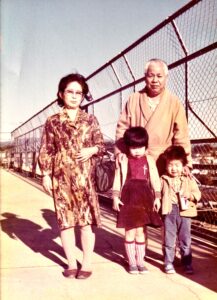☆かかとがぴたりとフィットする
足の形は千差万別であるとは何度も書いた。その足を外形でおおまかに分ければ、太く力強い足と、細く繊細な足ということになる。そして、その両者で選ぶべき靴が異なる。特に靴のかかとの形状である。
足のかかとを包み込む靴の部分をカウンターという。そして、このカウンターには柔らかいカウンターと、固くしっかりしたカウンターがある。そのどちらを選ぶべきなのか。
太く力強い足の持ち主は、ぴったりしてさえいれば、どちらを選んでも構わない。慎重にカウンターを選ばねばならないのは、細く繊細な足の持ち主だ。
「はい、そのような足をお持ちの方は、出来れば固いカウンターの靴をお選びいただきたいと思います」
細い足の持ち主は、足首も細く弱いことが多い。そんな足で柔らかいカウンターの靴を履くと、カウンターがかかとを固定してくれないため、段差を踏み間違えた時などにかかとが一方に滑り、足首をひねってくじきやすいのである。固いカウンターの靴ならかかとをしっかり固定するので、その恐れは少ない。
そう説明しても、柔らかいカウンターの靴のデザインに惹かれ是非買いたいという客もいる。そんな時充さんはソールに詰め物をする。靴の中の足を上に持ち上げ、甲の部分でしっかりフィットさせるためである。
「こうすれば、くじく恐れは少なくなります。それでも固いカウンターの靴に比べれば、やはり危険度は大きい。本当は固いカウンターの靴をお買い上げいただきたいのですが…」
☆縫い目・継ぎ目に注意せよ
人の足は思った以上に敏感である。靴を履いた時にわずかでも違和感があると、やがて不快感から痛みに変わることがある。
「注意しなければならないのは、靴の中の縫い目です。それがわずかでも出っ張っていると、足は敏感に感じてしまいます。もちろん、当店ではそんな靴は最初から仕入れませんが」
スポーティに見せようという靴には、帯状の革を縫い付けたものがある。このように、部分的に革が二重になっている靴も要注意だ。当然のことだが二重になっているところは革が分厚くなり、そこだけ伸びが悪いからだ。
「二重になっていない部分は足の形に従って革が伸びます。ところが2重になっていることころは伸びてくれず。そこだけ革のベルトでしめあげたようになってしまい、足を傷めてしまうことがあります」
特に、親指と小指の付け根より先が2重革になっている靴は注意したほうがいいと充さんはいう。
クイーン堂シューズにも、そんな靴は置いてある。スポーティな靴を好む客のためだ。
「そんな靴は試し履きをしていただいた上で、足の形に合うようにストレッチャーで2重革の部分を伸ばして差し上げるようにしています」
☆サンダル
蒸し暑い日本の夏は、足も出来るだけ涼しくしてやりたい。夏場にサンダルを履く女性が多い理由である。だが、サンダルもよく選ばないと、足のトラブルを抱えることになる。
いけないのは、足より大きめのサンダルだ。ややもすると、足が前に滑り、指がサンダルの前に出る。
「そんなサンダルを履いていると、足を縁石や階段にぶつけ、けがをしてしまうことになります」
では、指が前に出なければいいのか。
「いや、サンダルもできれば足が滑らないように固定してやりたいのです。甲の部分で固定されないと、足が前に滑って狭くなった先の方で指が締めつけられます。そすれば、外反母趾などを引き起こす恐れがあります」
そんなわけで、出来ればストラップ付きのサンダルを選んで欲しい、というのが充さんの意見である。ストラップは足が滑らないように固定してくれるからだ。
写真=クイーン堂シューズお勧めのサンダル。足が前に滑らない形状で、ストラップ付きもある