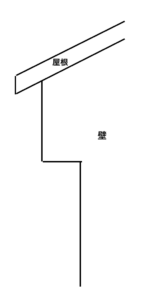「商店街の靴屋で最後に靴を買ったのはいつだったろう?」
そうなのである。いま、町から靴屋さんが急速に姿を消している。
1985年、全国に約2万7600店あった靴屋は2021年、5083店舗にまで減った。総務省統計局と通商産業省が実施する「経済センサス」の数字である。わずか40年足らずで4分の1になってしまった。さらに5083店舗は5年前の調査に比べると1124店舗の減少だ。町の靴屋さんの廃業に歯止めがかからない。
原因はいくつかある。まず、大手チェーン店の台頭である。2023年時点で最大手のABC-MARTは全国に1081店舗を展開、2位の東京靴流通センターも507店舗を開いている。この2社だけで全体の3割以上を占める。
オンライン通販の台頭も目覚ましい。Amazon、楽天、ZOZOTOWNなどがサイズ交換、返品対応を充実させて店舗に足を運ばなくても安心して靴が買えるようになった。
それに少子高齢化が追い討ちをかけ、さらに都市部ではテナント料・人件費の高騰が加わる。町の靴屋さんが生き残ることが出来る隙間が年々狭くなっている。
こうした大きな流れは、当然桐生でも起きた。織物で繁栄を極めた時代を持つ桐生には、かつて30を超す靴屋さんが軒を並べた。しかし大手チェーン店の進出、ネット通販の普及という全国に吹く逆風に加えて、桐生には繊維産業の衰退、急速な人口減少という嵐が吹き荒れた。2005年に旧新里村、黒保根村と合併した時は13万2443人だった人口は2025年5月、とうとう10万人を割り込んで9万8224人になった。町の靴屋さんは全国以上の早さで姿を消していった。いま、いわゆる町の靴屋さんはたった3店舗しかない。
ご紹介する「クイーン堂シューズ」は、生き残った3店舗の1つである。桐生市の目抜き通りである本町通のほぼ中央、本町4丁目にある店舗は、間口3m弱、店内は100㎡に足りない。だから店内に展示できるのは200足ほどでしかない。広い店内に所狭しと靴を並べるチェーン店に比べれば品揃えははるかに見劣りする。
ところがこの店、驚くほど商圏が広い。客は桐生市内や隣接するみどり市、伊勢崎市、太田市、栃木県足利市だけでなく、車を使っても1時間以上はかかる高崎市、前橋市、沼田市、埼玉県熊谷市からも、わざわざこの店に靴を求めに来る常連さんが100人以上もいるのだ。
なぜ、こんな地方都市のちっぽけな靴屋に遠路はるばる足を運ぶ客がいるのか?
クイーン堂シューズの4代目、小泉充(たかし)さんが展開するFacebookやインスタグラムへの書き込みを見て、
「ひょっとしたら、そうなのか?」
と閃くものがあった。
書き込みはこんな具合である。
「さすがクイーン堂さん!!履きやすくて素敵な靴が必ず見つかります★」
「快適に歩けるシューズを買いました(^O^)/私の変な足を理解して歩きやすい靴を提供してくれる【クイーン堂シューズ】さんいつもありがとうございます(*^o^*)。ちびっ子な私が嬉しいインソールだし 早速履いて歩いたけど 足がひっくり返る事もなく歩けた!!良かった♪♪」
この店が遠方の客も引き寄せているキーワードは、どうやら
履きやすく、快適に歩ける靴
らしいのだ。
だが、クイーン堂シューズはひとりひとりの足に合わせて靴を作る靴工房ではない。メーカーが大量生産する既成靴を仕入れて販売する靴屋さんである。チェーン店を含めたほかの靴屋さんと同じではないか。それなのに、クイーン堂で売る靴がほかの靴屋で買う靴より履きやすいということがありうるか?
どうにも納得できない。納得するには話を聞くしかない。私は取材を始めた。
写真=クイーン堂シューズ。左から小泉充さん、琛司さん、民子さん