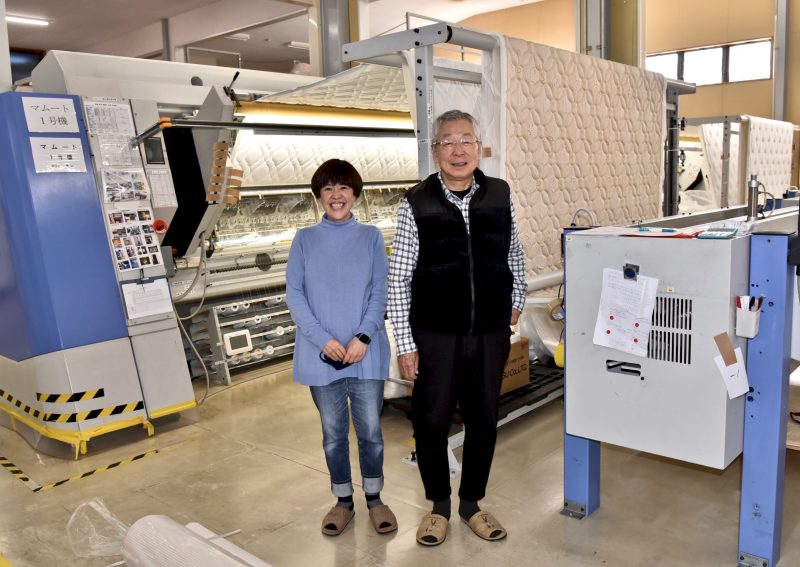【桐生ならばこそ】
金加の前身は、産地商社ともいえる買継商である。父・亥嘉造さんが昭和25年(1950年)5月、群馬県北群馬郡榛東村から桐生市に出て来て興した。起業から間もなく朝鮮戦争が勃発、繊維産地である桐生は戦争景気に沸いた。創業間もない金加にも大量の注文が押し寄せた。豊かな買継商の長男として何不足なく小学校6年生になった金井さんは、作文に
「家の仕事を継ぐ」
と書いた。
だが、子ども時代の夢を持ち続ける人は少ない。金井さんは中学生になると音楽にのめり込み、高校ではロックバンドを組んだ。大学を出るころには初志はどこかに行ってしまい、就職して給料のほとんどを楽器につぎ込んだ。フェンダー、ギブソン……、ギター好きの誰もが憧れる楽器で金井さんの部屋が埋まって行った。
仕事を辞め、家業に入ったのは就職して1年半ほどたった頃である。
「父に『車を買ってやるから戻ってこい』っていわれてコロリと変わっちゃった。だから、たいした跡継ぎじゃなかったね」
そんな金井さんが、後に世界の何処にもないキルティング関連の機械を次々と生み出すのだから、遅ればせながら金井さんは初志を貫徹したことになる。
それまで会社に勤めながら休日はバンド活動でステージに立ち、ギャラも得ていた金井さんが、今日は東京、明日は大阪と営業に飛び回り始める。
「ええ、時間の99%が仕事になりました」
客の求める生地を聞き出し、桐生の機屋に注文を出す。子どもの時からの友人には機屋の子弟がたくさんいた。彼らに客の注文を伝えると、他の仕事を押しのけてでも織ってくれる。時間ができると機屋を回った。遊びに行くのではない。それぞれの機屋の得意分野を頭に詰め込むためだ。繊維産地・桐生だからできたことだ。
「こんな生地、織れないかなあ?」
多分、他ではできないといわれたのだろう。客からそんな相談を持ちかけられれば金井さんは桐生にとって返し、織れそうな機屋に話を繋ぐ。織り上がれば生地を納める。できなければ、なぜ織れないのかを客に説明する。
金井さんへの客の信頼が日々増した。
【機屋へ】
客からの信頼は高まっているはずなのに、買継ぎの仕事は徐々に減った。中間を省いて流通を合理化する動き、いわゆる流通革命が繊維業界にも押し寄せたのである。
それを見て取った金井さんは金加をテーブル機屋に変身させる。織物産地と都会の問屋を繋ぐだけでなく、機を織るのに必要な紋紙、糸、架物、ジャカードなど機を織るのに必要な資材を小さな機屋に供給し、企画した生地を織ってもらうのである。工場を持たない製造業、いまでいうファブレス経営を取り入れたのだ。そして、ベッドを覆うマット用の生地に生産の重点を起いた。暮らしの洋風化が進み、需要が旺盛だったからである。
仕事が増え、捌ききれないほどになった。仕事に追われる日々を過ごしながら、金井さんは2つの問題に気が付いた。