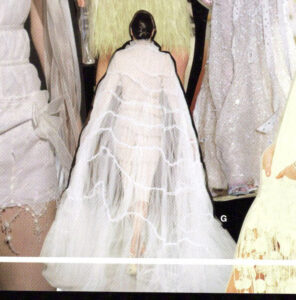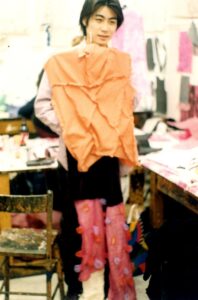日本に戻って森英恵さんからの注文は納品したが、ほかに仕事の当てはない。やむなく、自分のデザインの著作権を売り始めた。1件5万円。だが、まだデザイナー・片倉を知る人は少ない。生活を支えるほど売れるものではない。
「だけど、実家に戻っていたし、パリで仕事も住む家もなく、途方に暮れていたころに比べれば、まだましではないかと自分に言い聞かせていました」
それに、少ないとはいえ、自分のデザインを買ってくれる人もいる。
「なんとか生きていれば、いずれ作品が認められ、仕事ができるようになるのではと思っていたんです」

さて、これからどうするか。そんなことを考えているうちに、留学中のロンドンで見たテキスタイルを思い出した。桐生在住の故・新井淳一さんのテキスタイルである。
それは、美術館のテキスタイル・コーナーに展示されていた。そこでは16世紀ぐらいからの様々な布地を見ることができたが、新井さんの作品が際立っていた。月に1、2回はこの美術館に通い、新井さんの作品に見入った。
「高度なテクノロジーとクラフト、つまり高度な技術と工芸的な手作り感が同居しているんです。ローテクの雰囲気があるのに、調べてみるととんでもないハイテクが使われている。これ、何なんだ?」
新井さんに会いたくなった。帰国から間もなく電話で連絡を取ると、手術からの回復途上でいまは会えない、とのこと。
「秋においでなさい」
確か10月だった。桐生市境野町の新井さん宅を初めて訪ねた。痩身。眼鏡の奥の目が厳しい。
新井さんは世界が認めるテキスタイル・プランナーである。憧れて会いに来る人は多いらしい。そういえば、ロンドンで一緒に学んだ友人も、新井さんを訪ねたといっていた。
片倉さんは自分の来歴を語った。デザイナーを目指してロンドンに留学した。ロンドンの美術館で新井さんの作品に出会い、何度も訪れ、新井さんの作品を評した本も沢山読んだ。知れば知るほど、新井さんの作品のすごさに打たれた……。
聞いていた新井さんは、片倉さんに関心を持ってくれたらしい。
「ご一緒に食事をしませんか」
桐生市内のレストラン「芭蕉」でご馳走になった。食事をしながら、新井さんがいった。
「いまプロジェクトを手がけています。よかったら手伝ってくれませんか?」
自分の作品を桐生市の有鄰館をはじめ、東京や千葉で展示するのだという。無給である。だが、新井さんと一緒に仕事ができれば、金など問題ではない。得るものは山ほどあるはずだ。
喜んで引き受けた。
それから、少なくとも毎月1回は桐生に行き、新井さんの仕事を手伝った。展示会の準備だけではなかった。桐生市内の機屋、プリーツ工場、糸商などとの打ち合わせに同行した。一緒に桐生市内の群馬県繊維工業試験場に行ったこともある。新井さんは様々な職種からノウハウを吸い取り、繊維工業試験場の設備、科学知識までも取り入れてどこにもないテキスタイルを創り出していた。
新井さんが亡くなったのは、2017年9月25日である。すでに桐生の笠盛で働いていた片倉さんは、もちろん葬儀に参列した。
「いまでも、新井さんの作品は輝きを失っていません。もっと長く生きて、新しい作品を見せてもらいたかった」
片倉さんは新井さんの冥福を祈った。