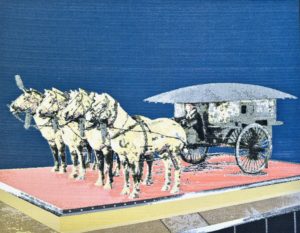【捺染】
布の染色法は「先染め」と「後染め」に大別出来る。先染めは布にする前、つまり原料や糸の段階で染め、機屋さんは色の付いた糸で織ったり編んだりする。後染めは布に仕上げた後で色をつける。
「捺染(なっせん)」は後染めの手法の1つである。「捺」とは、押す、押さえつける、という意味で、染料と糊などの接着剤を混ぜ、布に押しつけて染める。木版や銅版に色を載せて紙や布に写す版画や、活版印刷も「捺染」の仲間といえる。原理が簡単なためか捺染の歴史は古く、紀元前2000年頃にはヨーロッパで使われていたといわれる。
繊維製品の捺染には、凹凸のついたローラー(こちらに染料を乗せる)と圧着用のローラーの間に布を通して染める機械捺染と、すべてを手作業で進める手捺染がある。手捺染はシルクスクリーンを張った型枠の上に置いた染料をへらで伸ばして1枚ずつ染める。シルクスクリーンはメッシュになった織物と紫外線で硬化する感光剤の2層構造で、染める絵柄を何かで覆って紫外線に晒したあと洗うと、紫外線を浴びていない部分の感光剤だけが洗い流され、染料を通すようになる。少し年配の方なら、ガリ版印刷と同じ仕組みといえば頷いていただけるのではないか。
平賢は手捺染専業である。五月の空を泳ぐ鯉昇り、夏を彩る祭半天を染め続けてきたが、少子化や庭のない暮らしが広がって鯉のぼりの需要が減り、経営環境は年々厳しさを増す。愚痴の一つも出て来そうな時代だが、小山哲平専務は「逆境こそチャンス!」といわんばかりに新規分野の開拓に取り組む。
「捺染で、もっとできることがあるはずなんです」
2020年、その努力が小さな芽をつけ始めた。
【常識破り】
捺染業というのは、依頼主の注文に従って布を染める仕事である。どれほど技を凝らして染め上げてみても、何処にも染め主の名は現れない。同業者間の競争に晒されて値引きを迫られ、工賃の決定権もない。典型的な下請け仕事である。平賢も例外ではなかった。
だから、その注文が入った時、小山さんは自分の耳を疑った。
「予算が100万円以上あります。この金額で染められる枚数だけ染めて下さい」
2020年秋の中頃である。まず電話で
「ご相談したい」
と接触があり、1週間もたたないうちに来桐した担当者がそう切り出したのだ。予算内で染められる枚数だけ? 極端な話、
「1枚しか出来ません」
ということだって出来る。捺染業界からすれば、常識破りの注文である。